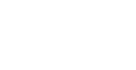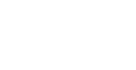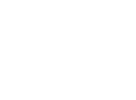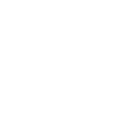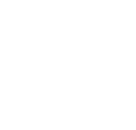ニイガタビト
ローカルカメラマン最高!【前編】
- 田舎からだからこそ、見つけた自分のスタイル -
2017.07.20 掲載
前編
ヒロスイ写真館代表、カメラマン
酒井大さん
南魚沼市在住
前編

越後山脈や三国山脈に囲まれ、国内有数の豪雪地として知られる南魚沼市。自然豊かなこの地で活躍するカメラマンがいます。
酒井大(ひろし)さん36歳。2014年に自身のあだ名を冠にした「ヒロスイ写真館」を起業。基本的にどこへでも伺って撮影する「出張写真館」として、広告、人物、物撮り、スナップ撮影など幅広く対応しています。
今秋には3児のパパとなる予定の酒井さんがローカルカメラマンになった経緯や、どんな想いで活動をしているのか?根掘り葉掘りお聞きしました。

酒井さんは、1981年1月・魚沼市(旧北魚沼郡守門村)生まれ。中学生の頃に自宅で古い一眼レフカメラを見つけたことをきっかけにカメラの魅力に取り憑かれました。六日町高校に進学すると写真部に入部。毎日のようにカメラを首から下げて通学していたそうです。
「当時は田舎だったしフォトグラファーという言葉も周りのみんなはピンと来なくて、『電車を撮るの?』なんてちょっとしたオタク扱いでした。進路を考える際に、自分は何者なのか?将来何をしたいのか?と自問した時に、やっぱり大好きなカメラで食べていきたいと思いました」
1999年に写真学科のある大学に進学。東京でカメラの専門的な勉強をはじめた当時は「新潟に未練はない。東京でカメラマンとして名をあげるぞ!」という気持ちだったそう。

2003年に大学を卒業すると、まずは個人のプロカメラマンのアシスタントを経験。「数ヶ月も休みがないくらい仕事が来る人でした。一日に複数案件をこなすこともざら。自分も初めてで分からないことだらけ、とにかく怒られてばかり。めちゃくちゃ厳しい現場でした」と酒井さん。フリーのプロカメラマンの仕事を間近で見れたのは良い経験だったそうです。
その後に、アシスタントとして入った大手印刷会社の写真部は全く雰囲気が違ったと言います。「フリーと社員カメラマンではマインドがぜんぜん違う。大手は営業チームと撮影チームが分かれているので、どこか余裕がある印象。30人位カメラマンが所属していて、現場のスケジュールにも余裕があり、撮影技術はしっかりしていて勉強になりました。この時の撮影現場の経験が、今の仕事の役に立っていますね」。
アシスタントとして貢献していた酒井さんに、この大手印刷会社から「正式に社員として働かないか?」という打診がありました。入社すれば安定して一生過ごせるかもしれない。しかし、会社員として写真部で働いていくイメージがどうしてもわきませんでした。
「フリーカメラマンに付いた時も、大手印刷会社でも、今思えば生意気なんですけれど、もっと作家性を出した面白い写真を撮りたいとずっと思っていました。カメラマンの名前の出ない仕事が大半。そういう仕事はとても大切だけれど、当時は依頼された商用写真の撮影を淡々と自分ができると思えなかった。若かったし、作家・アーティストになりたかったんですね」

アーティストとして活躍したいと思っていた酒井さんは、会社勤めの傍ら、プライベートで作品となる写真を撮る日々を送っていました。しかし、次第に作品作りも行き詰まっていきます。
「どういう写真で世の中から注目してもらうか?を考えると、“今までにないもの”、“エッジの立った表現”が必要です。誰かの真似ではダメで、オリジナルのものを見つけないといけません」
過去には様々なカメラマンが衝撃的な作品を発表している。今現在もゴマンといるカメラマンが最新の表現を競って探している。氾濫する情報に影響を受け、何か撮ろうと思っても「あれ…これは誰かの真似しちゃっているじゃん…」と自問自答する日々に、心が疲れていきました。
「いつの間にか“自分が撮りたいもの”じゃなくて、“誰もやったことがないこと”を探すようになっていました。やってないもの探しばかりしていると、それって俺がやりたいことなの?やりたくないことなの?撮りたいものを撮るのがいいの?撮られていないものを撮るのがいいの?何が良いのかわからなくなってしまいました」

会社員として商業写真を撮っていく覚悟もできず、作品もイマイチ。東京でもがき苦しむうちに、東京そのものが嫌になっていったそうです。
「都会はコンクリートジャングルと言いますが、本当に壁だらけですよね。まるで、壁の中から出て壁の中へ移動している繰り返し。そんな空間に息が詰まる様になり、創作意欲も半減していきました」
一方、故郷の新潟はいわゆる「抜け」が気持ちよかった。遠くの山まで見える景色。真っ白に広がる雪原。空を写す水を張った一面の田んぼ。その風景ひとつひとつが気持ちよくて、感動したといいます。
「壁に囲まれて、何かいっぱいいっぱいになっていた。“抜けている”ことを渇望してました。結局、作品も、地元に帰ってきて撮った写真でつくっていた。アーティストとして自分なりの方向性を見いだせなかったし、東京にいる意味がないなと考えていました」
24歳の夏。「正社員に」という就職話を断り大手印刷会社を辞めたタイミングで、地元に帰り疲れた心を休めることにしました。事実上のドロップアウト。当時はUターン後もカメラを仕事にする気はあまりなかったそうです。
a
このページをSNSで共有する