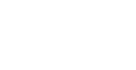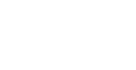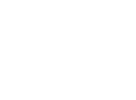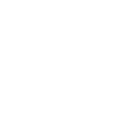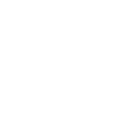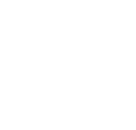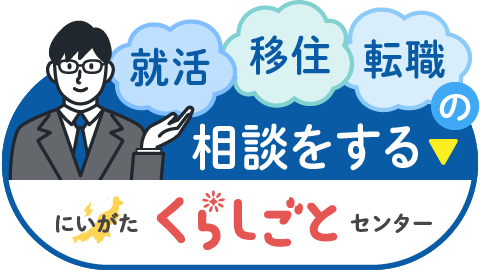ニイガタビト
中越大震災から10年
- 10年目の思い -
2014.10.15 掲載
中越メモリアル回廊「川口きずな館」 スタッフ
渡辺 千明さん
おぢや震災ミュージアム「そなえ館」スタッフ
細貝 悠斗さん
10月23日で中越大震災から10年を迎えます。10年という時間が過ぎた今も、震災に対する様々な思いを持って活動に取り組んでいる方がいます。今回は、自身も被災され、現在は中越大震災のメモリアル拠点として整備された「中越メモリアル回廊」に勤める、「川口きずな館」の渡辺千明さん、「おぢや震災ミュージアムそなえ館」の細貝悠斗さんにお話を伺いました。
旧川口町(現在の長岡市川口地域)出身。高校卒業後、新潟県内の短期大学へ進学し、その後、東京都内の大学へ編入。大学卒業を控えた平成23年3月、東日本大震災で被災する。このことをきっかけにUターンを決意。平成24年4月から特定非営利活動法人くらしサポート越後川口の職員に採用され、「川口きずな館」のスタッフとして勤務している。
「東京で学生生活を過ごしていましたが、卒業後は東京か新潟のどちらかで就職できればと考えていました。そう思いながら就職活動をしていたなか、東日本大震災に遭いました。仮に東京で就職しても、いずれは新潟に戻ることを漠然と考えていましたが、この震災をきっかけに「地元に貢献したい」と思い、川口に帰ることを決めました。そのときは直感で決めたのですが、これは、私が中越大震災を経験したことが関係していたと思います。
中越大震災のとき、私は高校生でした。発生当日は友人と長岡市内にいたのですが、しばらくは川口に帰ることができず、数日間は長岡市内の避難所を転々としました。また、川口に戻ってからも、自宅が全壊したため、避難所や仮設住宅での生活が続きました。そのような日々のなか、知人や見知らぬ人を問わず、多くの人から支援をいただき、周囲の優しさや人の温かさを強く感じました。私自身も家族や周囲のことを考えられるようになり、大人へと成長させてくれた出来事でした。こういったことを「3.11」が改めて思い出させてくれたのだと思います。」
「川口きずな館では、中越大震災からの復興の様子を年表や写真パネルなどを使って紹介しています。それと、「川口の5,000人の絆」として、中越大震災で被災した地元の人々やボランティアなどで川口地域の復興に携わった人たちの想いを集め、記録しています。集めたものは館内にあるiPadで誰でも見ることができます。
また、東日本大震災を始めとする各地の災害を支援するためのグッズを販売したり、館内にある「きずなカフェ」のメニューとして、被災地で作られたコーヒーなどを提供することもしています。その他にも、様々なイベント会場として活用されるなど、きずな館は川口地域に暮らす人や川口を訪れる人の交流拠点ともなっています。私は、きずな館を訪れる人に館内を案内したり、川口地域の人々の活動を紹介しており、また、各団体が実施するイベントのサポート活動などを行っています。」
「川口に戻ってきて、生まれ育った地域のことや町おこしの活動など、知らないことが多いと気付かされました。それらは、私が川口を離れている間に変わったり、新たに出来たものばかりではなく、昔から地域にあったものでした。そのことに気付かされ、ふるさとに対する意識が変わりました。それまでは、「自然の他には何もないところ」と思っていたのですが、実際には、誇れるもの、おもしろいものがたくさんあります。また、語れることも数多くあり、それらを多くの人に伝えたい気持ちでいます。私は今、震災発生から復興への道のりと、現在の川口地域の活動を紹介しているわけですが、特に、「今の川口を見てもらいたい」という思いが強くあります。地域を盛り上げようと頑張っている人たちが大勢います。多くの方からきずな館に足を運んでいただき、川口のことを知っていただき、好きになってもらいたいと思っています。」
「今年は、中越大震災から10年となりますが、川口地域では行政と住民の方が一緒になって「川口の次の10年」を考えました。アンケート内容の検討から結果分析まで、複数回のワークショップを重ね、多くの方から参加してもらいました。地域の人たちが自分のことと考え、積極的に参加していただいたことをうれしく思っています。
川口に戻って3年以上が過ぎましたが、近くに家族や友人がいることの安心や幸せを感じることができ、戻ってきてよかったと思っています。そして、地元に貢献できる現在の仕事にやりがいを感じているので、この後もずっと活動を続けていくつもりです。確かに、川口は小さい地域ですが、小さいからこそできる活動があると思っています。それを模索していくことが、これからの私のテーマとなりそうです。」
小千谷市出身。高校卒業後、静岡県の大学に進学し、環境防災学を学ぶ。平成23年10月、大学4年生のときに臨時職員として「おぢや震災ミュージアムそなえ館」のオープンに携わる。翌年4月から、一般財団法人小千谷市産業開発センターに所属して「そなえ館」のナビゲーターを務めている。
「高校を卒業し、静岡県の大学に進学しましたが、そこでは環境防災学を勉強しました。環境防災学とは、自然の保護や再生を考えながら、その自然のなかで起こりうる災害に備えることで、安全で安心な暮らしを目指していくという学問です。防災の分野に関心を持ったのは、中越大震災で被災したことがきっかけでした。
震災発生時、中学生だった私は学習塾で勉強していました。揺れが収まってしばらくしてから外に出ると、真っ暗で、住んでいたところではないような、見たこともない風景だったことを覚えています。当日の夜は地域の体育館で過ごし、また、電気が復旧するまでの1週間は地元の高校のグラウンドに張られたテントで生活をしていました。不安で落ち着かない気持ちになりましたが、それと同時に「災害に備える」という意識が芽生えました」。
「就職は、大学で学んだことを生かしたいと考えていました。進学先の静岡県に残る選択肢もあったのですが、大学4年生のとき、知人から「そなえ館」を紹介されてUターンを決めました。大学に入学した当初から、卒業後は地元に戻りたいと思っていたこともあり、学んだことを生かせる「そなえ館」のオープンは絶好のタイミングでした。
「そなえ館」は「楽しく学んでそ・な・えましょ!」をコンセプトに、地震のことを学び、防災について考えるきっかけづくりの施設となっています。館内には中越大震災についての写真パネルや展示物があり、発生から3時間後、3日後、3ヵ月後、3年後と時間経過をおって被災地の様子を知ることができます。また、地震動シミュレーターを使って、中越大震災と同じ横揺れを体験することなどもできます。
来館していただくのは、防災や地震について学ぶ目的を持った、町内会や自治会などの自主防災組織の方や小中学生が中心ですが、観光で来た方も立ち寄られます。県外からも多くの方が来ています。目的を持って来た方にはより知識を深め、観光で来た方には少しでも興味や関心を持ってもらえるよう、帰るときには来館前より意識を高めることができればと心がけています。」
「私が皆さんに知ってもらいたいのは、「災害は身近なもの」ということです。災害は事前に予測不可能なもので、いつ、どこで発生するか分かりません。多くの人は「自分の身の回りで起こるはずがない」と思っているかもしれませんが、その考えが一番危険だと思います。いざというとき、知っていると知らないでは生命にかかわってくるかもしれません。「自分の命は自分で守る」が基本にあると思います。
しかし、現実として、常時、災害を意識して生活することは難しいです。だからこそ大勢の方から「そなえ館」に来て、展示品を見たり、シミュレーターを体験したり、私たちナビゲーターや語り部の方の話を聞いていただきたいと思います。そうすることで、ここで見聞きしたことが頭の片隅にでも残り、いざというときに役立ててもらえると考えています。」
「小千谷に戻ってきて一番良かったことは、「人とのつながり」を実感できることです。仕事を通じて知り合った地域の方や語り部の方から学ぶことも多くあります。そして、何よりも近所のつながりがあるという安心感があります。実際に中越大震災のときも、近所の人たちとつながりがあったからこそ、助け合いながら頑張ることができました。
今後、取り組みたいと考えていることは、地域のなかで子どもたちと大人をつなぐ仕組みづくりです。例えば、地域の清掃活動を子どもも一緒に行い、そのときに危険箇所を想定したり、避難場所を確認するなど、地域ぐるみで防災に取り組むサポートができたらと思っています。
「そなえ館」で活動を始めて3年となりますが、これまではその時々に対応するだけで精一杯でした。これからは、自分なりの工夫を重ねながら、思いが伝わるような仕事をしていきたいと考えています。」
※「niiGET」Facebookで細貝さんのメッセージ動画を見ることができます。
このページをSNSで共有する